| 小児科 |
|
| 大切なあかちゃんを守ってあげる。よくある感染症、予防接種など知っておくべき事ををご紹介します。 |
| なお、当ホームページの予防接種などの情報更新は怠りませんが時事の状況により詳細が変更になりますのでその旨ご留意のうえ情報活用ください。
|
 |
よくある感染症
| 代表的な感染症について、症状と病名を列挙しました。 以下の症状が該当したら早めのご来院をお勧めいたします。 |
 |
| 病 名 |
症 状 |
| 麻 疹 |
熱が先行しその後湿疹が全身に出てきます |
| 風 疹 |
3日はしかといわれ全身に湿疹が出て3日間で治ります |
| 水 痘 |
全身に3−5mm径の水疱が出る病気です |
| 突発性発疹 |
3日間高熱が出て解熱後にからだに発疹が出ます |
| インフルエンザ |
急激に高熱が出て咳と鼻の感冒症状があります |
| 溶連菌感染症 |
のどに膿がつき全身に赤い湿疹がでます |
おたふく
(流行性耳下腺炎) |
耳の下がはれて熱と痛みがでます |
りんご病
(伝染性紅斑) |
ほっぺがりんごのように赤くなります |
| マイコプラズマ |
高熱が出て咳がひどく止まりません |
|
赤ちゃんのお薬の飲ませ方
| お子さんに薬をきちんと飲ませる事はお母さんの大切な役割です。ここでは薬の飲ませ方のいくつかのヒントを書き出してみました。どれがベストであるというものはありませんので、それぞれ試してみながらお子さんにあったやり方を探してみて下さい。 |
- 水薬はそのまま飲ませます。粉薬はごく少量の水に溶いて'だんご状'にして上あごやほっぺの裏にこすりつけ、その後で水、湯冷まし、ミルクなどを与えます。
- 溶かすときは一口でのめる量にして、スプーンで流し込みます。
- ジュースやスポーツドリンクに混ぜる場合は、薬によってはかえって苦みが増す場合があるのでご注意ください。
- 水に溶かし凍らせてシャーベット状にする方法もあります。夏場には良いかもしれません。
|
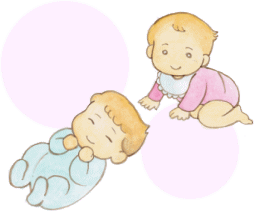 |
子供の予防接種について
赤ちゃんは病気に対する抵抗力(免疫)をお母さんから分けてもらいますが、生後3〜8ヵ月程度でその力は消えてしまい後は赤ちゃん自身の力で免疫をつけなくてはなりません。そのお手伝いをするのが予防接種です。
予防接種は毒を弱めた細菌から作った“ワクチン”を体内に投与しそれと闘うことによって病気に対する抵抗力(免疫抗体)をつける方法です。
言うなれば病気と戦うまえの予行演習といえるでしょう。
また、予防接種の対象の病気のほとんどは伝染病です。予防接種には赤ちゃんや子ども自身の健康を守るだけでなく、みんなが接種することによってその病気が流行するのを防ぐ効果もあるのです。 |
予防接種 ワクチンの種類
予防接種のワクチンにも以下のような分類があり、それにより予防接種の受け方が変わってくるので注意が必要です。
担当医師とよく相談されて行ってください。 |
- (1) 生ワクチン
- 生きた病原体の毒性を弱めたもの。予防接種によって、身体はその病気にかかったのに近い免疫(抗体)を作る。(ポリオ、はしか(麻しん)、風しん、BCG等)
- (2) 不活化ワクチン
- 病原体を殺して免疫を作るのに必要な成分だけを取り出して作ったもの。複数回の接種が必要なケースが多い。
(百日咳、日本脳炎等)
- (3) トキソイド
- 不活化ワクチンの一種、細菌の出す毒素を取り出し無毒化したものをトキソイドという。免疫原性は保持したまま無毒化するので、このトキソイドを体内に注射すると、毒素を中和する抗体ができる。(
ジフテリア、破傷風等)
|
 |
|
ワクチンの接種スケジュール一覧表
|
|
- ※スケジュール管理は親の責任
- 予防接種の種類が多く、中には一定期間内に複数回受けなくてはならないものもあります。
くれぐれも“接種忘れ”のないように注意。
- ※予防接種の注意
- 予防接種は種類によりすぐに他の予防接種が受けられないケースもあります(同時接種ができるものもある)。ワクチンの種類によっては、それぞれ以下のような間隔を開ける必要があります。予防接種のスケジュールを立てるときには医師と相談してこの点を充分に考慮する事が必要です。
|
|